はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。
今回は、公認会計士が行う事業再生や廃業の支援についてご説明したいと思います。
公認会計士の中小企業支援
全国の中小企業支援の現場においては、多くの公認会計士が高品質な業務を提供していますが、その認知度は、税理士などの他の士業の方に比べると高くはありません。
そこで、日本公認会計士協会は、「中小企業支援は公認会計士にお任せください」というリーフレットを作成して、企業の全てのライフステージにおいて様々な種類の業務を提供できるため、公認会計士は大企業だけでなく、中小企業の方にもお役に立てることを説明しています。
今回は、このリーフレットにある成長支援の紹介をします。
ライフステージ別の公認会計士の支援についてはこちら
公認会計士が行う中小企業支援 | 創業期
公認会計士が行う中小企業支援 | 成長期
公認会計士が行うM&A,上場,事業承継の支援
公認会計士が行う事業再生・廃業の支援
事業再生の支援
様々な種類の事業再生の方法とその効果について詳しい公認会計士が、重要な経営課題に関して、原価管理や経営分析に及ぶ財務と税務の全般についての助言を行います。
再生を目指す会社 ( 債務者 )、債務者である金融機関や取引先などの利害関係者に対して、公正なる第三者としての立場から、有益な経営情報を提供することができます。
また、支援内容によっては、債務者側または債権者側どちらかの側に立ってサービスを提供することもできます。
廃業の支援
事業を廃業するにあたっては、会社組織を清算したり、他の事業者に移転・承継させたりと様々な方法がありますが、それらの場面においても公認会計士はお役に立つことができます。
廃業する際には、経営者とその家族だけではなく、金融機関、取引先、従業員など多くの利害関係者が生じますが、公正なる第三者としての立場から、有益な経営情報を提供することができます。
また、支援内容によっては、一定の利害関係者の側に立ってサービスを提供することもできます。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。


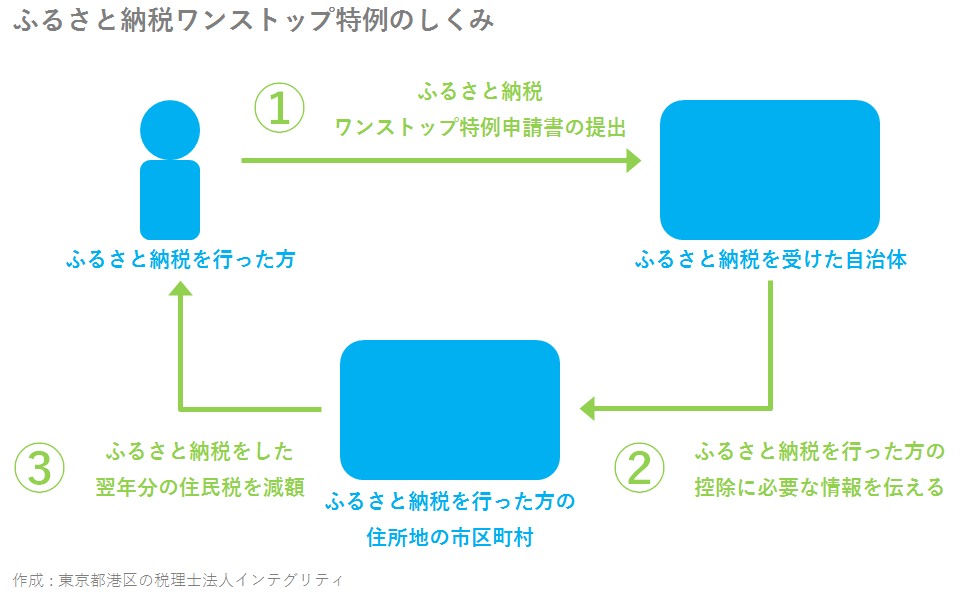
最近のコメント