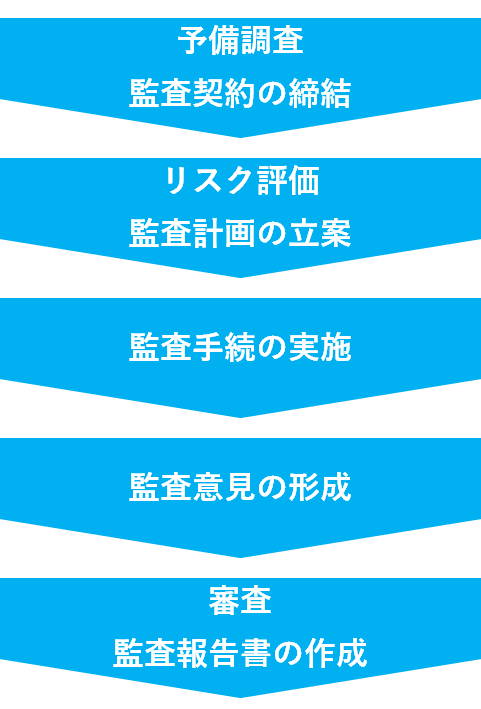はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。
今回は、青色事業専従者やパート・アルバイトなど、年収が103万円以下であっても扶養控除申告書が必要になる理由について説明したいと思います。
年収103万円の壁
年収103万円の壁、という言葉を聞いたことがある方も多いと思います。
年間の給与収入が103万円以下であれば、
- 本人に所得税がかからない
- 配偶者控除の対象になる
- 扶養控除の対象になる
といった税金の優遇を受けられることをいいます。
青色事業専従者や、パートやアルバイトをしている配偶者(妻または夫)や扶養親族(子供など)の方は、この103万円の壁を超えないようにしている場合が多いと思います。
年収については、この103万円の壁以外にも、98万円の壁、130万円の壁、141万円の壁といったものがあります。これらの年収の壁については下記ページを参照ください。
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります
年収103万円以下でも所得税がかかる場合あり
年収103万円以下でも所得税がかかる場合があります。
会社に「扶養控除申告書」を提出している場合
年収103万円以下で所得税がかからないのは、会社に「扶養控除申告書」(正式名は給与所得者の扶養控除等(異動)申告書です)を提出している場合になります。
会社に「扶養控除申告書」を提出していると、会社が年末調整をしてくれるので、年収103万円以下であれば、年末調整の結果、所得税はゼロになります。会社が全てやってくれるので、自分で何か手続きをする必要はありません。
また、会社に「扶養控除申告書」を提出していると、毎月の給料から天引きされる所得税の額も少なくて済みます。月の給料が88,000円未満であれば、毎月の給料から天引きされる所得税(源泉所得税)もゼロになるので、毎月の手取りが減りません。
パートやアルバイトだけでなく、青色事業専従者の方も「扶養控除申告書」を提出してくださいね。
会社に「扶養控除申告書」を提出していない場合
年収103万円以下であっても、会社に「扶養控除申告書」を提出していない場合は、面倒になってしまいます。
所得税をゼロにするためには、確定申告をして、給料から天引きされた所得税を返してもらわなければなりません。確定申告をしないと、給料から天引された所得税は戻ってきません。青色事業専従者であっても同様です。
会社に「扶養控除申告書」を提出していないと、会社が年末調整をしてくれないので、自分で確定申告をする必要があるのです。
また、会社に「扶養控除申告書」を提出していないと、毎月の給料から天引きされる所得税の額も大きくなってしまい、毎月の手取りが減ってしまいます。(確定申告すれば、天引きされた所得税が戻ってくるので、結果的には所得税はゼロになります。)
おわりに
繰り返しになって恐縮ですが、青色事業専従者の方で「扶養控除申告書」を提出するのを忘れてしまうケースが少なくないのでご注意ください。
港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。