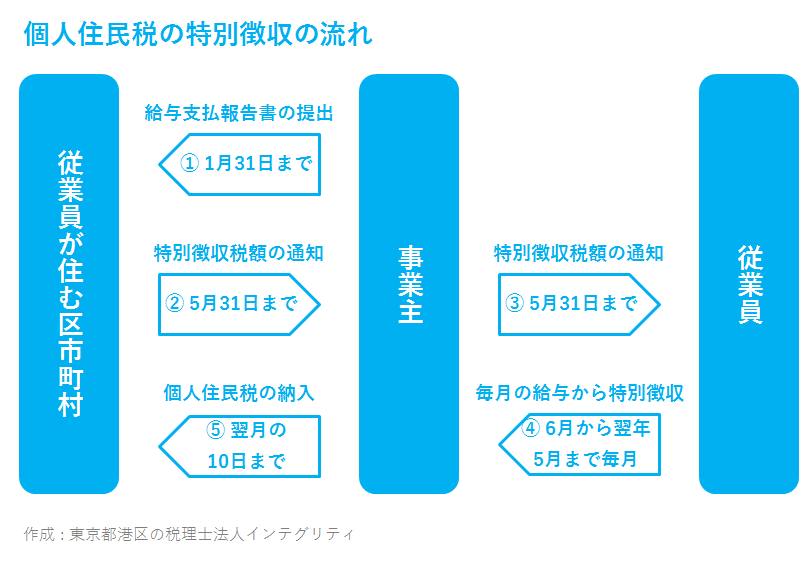はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税について解説します。
今回は、5,000万円を超える海外資産がある人が税務署に申告する必要がある国外財産調書制度について説明します。
国外財産調書を提出しない場合の罰則などについては下記ページを参照ください。
5,000万円超の海外資産の申告にかかる罰則 | 国外財産調書制度-2
どのような有価証券や預貯金が国外財産に該当するのかについては下記ページを参照ください。
どのような有価証券や預貯金が国外財産になるのか | 国外財産調書制度-3
国外財産調書に記載する国外財産の金額については下記ページを参照ください。
国外財産調書に記載する財産の価格 | 国外財産調書制度-4
なぜ国外財産を申告しなければならなのか
なぜ国外財産を申告しなければならないのかというと、所得税や相続税などを適正に課して、その税金をしっかりと徴収するためです。
昔に比べて国外財産の保有が年々増加しており、それら国外財産についての課税の適正化をすすめるために、一定の国外財産を持つ人にその内容を申告してもらうという国外財産調書制度が平成24年の税制改正で導入されました。
国外財産調書を提出する必要がある人
税務署に国外財産調書を提出する必要がある人は、
非永住者以外の居住者で、
その年の12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を持っている人です。
なお、所得税の確定申告をしているかどうかは関係ありません。所得税の確定申告をしている人でも、していない人でも、上記に該当する人は国外財産調書を提出することになります。
居住者とは、その年の12月31日時点において、日本国内に住所がある人(または現在まで引き続き1年以上居所がある人)をいいます。
非永住者とは、上記の居住者のうち、日本国籍を持っていない人で、かつ過去10年以内に日本国内に住所(または居所)があった期間の合計が5年以下の人をいいます。
国外財産とは、国外にある財産のことをいいます。「国外にある」かどうかの判定は財産の種類ごとに行います。
- 不動産なら、その不動産が所在する場所で判定します。
- 預金なら、その預金の受け入れをした営業所などが所在する場所で判定します。
- 株式なら、その株式の管理口座が開設された金融機関の営業所などが所在する場所で判定します。
国外財産調書の提出
国外財産調書を提出する税務署は、
- 所得税の確定申告をする必要がある人は、その納税地を所轄する税務署
- 所得税の確定申告をする必要がない人は、住所地を所轄する税務署
になります。
国外財産調書の提出期限は、その年の翌年の3月15日です。
国外財産の価格
国外財産調書を提出する必要がある人は、5,000万円を超える国外財産を持っている人になりますが、その国外財産の価格は次のように判定します。
- その年の12月31日における時価または時価に準ずるものとして見積価格によります。
- 国外資産の日本円への換算は、その年の12月31日の外国為替の売買相場になります。
国外財産調書に記載する事項
国外財産調書に記載する主な事項は
- 国外財産調書を提出する人の氏名と住所、
- 国外財産の種類、数量、価格、所在(国外財産は種類別、用途別、所在別に記載します)
などになります。
おわりに
5,000万円を超える海外資産をお持ちの方は、忘れずに国外財産調書を提出してくださいね。金額の記載などややこしいところも多いので、国外財産調書を提出する必要がある方は税理士に相談することをおすすめします。
港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。