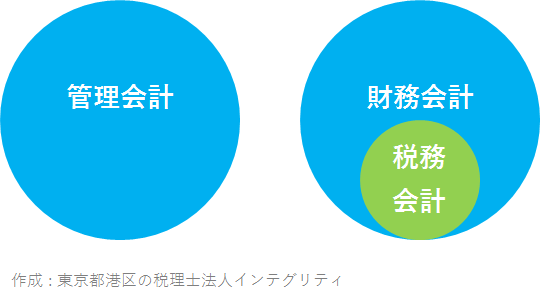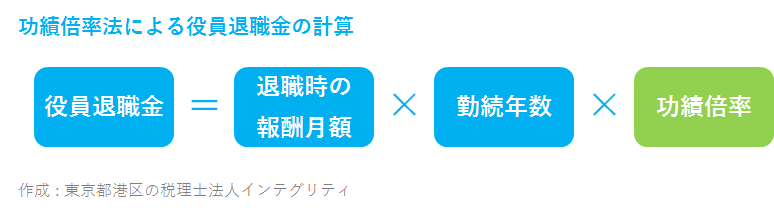はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
結婚式のご祝儀など、新札を用意しなければならない場面がありますよね。
今回は、そんな新札を入手する方法を紹介したいと思います。
平日昼間なら銀行の両替機で新札入手
お昼休みなど平日の銀行営業時間内であれば、銀行の両替機で新札を入手するのが簡単です。
銀行の両替機を利用するためには、その銀行のキャッシュカード(または両替機専用カード)が必要になりますので口座をお持ちの銀行に行きましょう。
銀行両替機の利用方法
- 事前にATMなどで現金を用意しておく
- 両替機に現金とキャッシュカードを入れる
- 両替後のお金を1万円に指定する
- 両替機から1万円の新札が出てきます
銀行両替機の注意点
- 両替機は銀行営業時間(平日の午前9時から午後3時まで)しか利用できません。ATMの稼働時間とは違うので注意してください。
- 両替機はキャッシュカードを持っていないと利用できません。キャッシュカードを持っている場合であっても1日1回しか利用できません。
銀行によっては両替機が置いていない支店もあります。その場合は銀行窓口で新札に替えてもらいましょう。口座を持っている銀行であれば、1日1回なら無料で新札に替えてくれます。
現金商売をしている方にはお馴染みの銀行両替機ですが、そうではない方が両替機と聞くと、大きなお金を小さい単位のお金に替えるイメージを持たれるかもしれません。しかし、銀行の両替機では1万円札→1万円札(新札)に替えることもできるので覚えておいてくださいね。
土日祝日や平日夜間ならATMで新札入手
平日昼間に銀行に行けない場合は、銀行やコンビニのATMで新札を入手できるかもしれません。可能性はなんとも言えませんが、新札が出てくるまでATMで入出金を繰り返します。手数料にも気をつけてください。
結婚式直前の場合は結婚式場やホテルで新札入手
新札を用意できないまま結婚式が直前に迫っている場合、結婚式場やホテルのフロントなどで新札に替えてもらえる場合があります。この方法か確実ではないので、結婚式場到着前に必ず電話で確認してください。
新札を手もとに
私のお客様である顧問先の会社の社長さんで、新札を何枚か財布に常備している方がいらっしゃいます。そのお方はまだ30代と若いのですが、ATMの利用などで銀行に行った際はついでに両替機を使って新札を用意して、現金で支払う場合はなるべく新札を使っているとのことです。
こういったさりげないスマートなお金の振る舞いを私も身につけたいところですが、今使っている財布は二つ折りなんですよね・・・
お財布つながりで下記ページもどうぞ
使う財布の値段の200倍が年収!?
おわりに
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。