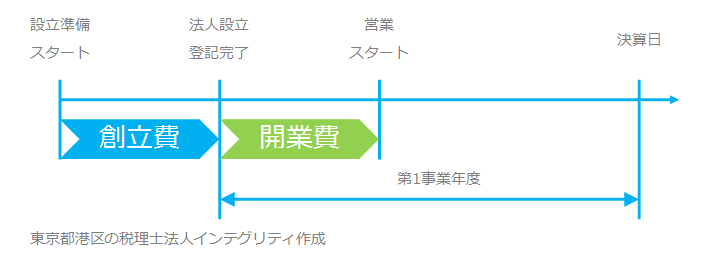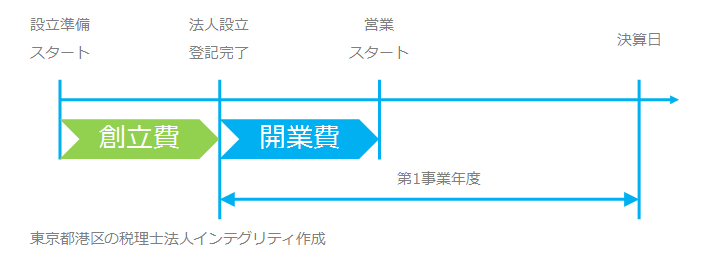はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
「社用車として車を買おうと思っているのだけど」と税理士に相談すると、多くのの税理士は4年落ちの中古車をすすめてくるでしょう。なぜ新車ではなく中古車なのでしょうか?なぜ中古車のなかでも4年落ちなのでしょうか?
今回は、そんな4年落ちの中古車が節税に使われるワケについて解説したいと思います。
新車は買ってもすぐには経費になりません
給料、事務所家賃、交際費など一般的な経費は支払ったときに経費になりますが、設備や機械などの固定資産を購入したときは、すぐには経費になりません。法定耐用年数に応じて数年かけて徐々に経費になっていきます。法定耐用年数とは、この資産ならこれぐらいの年数使えるだろうと国が定めた年数をいいます。
新車を買った場合もすぐには経費にならずに、6年かけて経費になります。例えば600万円で新車を購入した場合、6年かけて毎年100万円が経費になるイメージです(定額法の場合)。
中古車なら経費になるまでの時間が短い
固定資産を中古で買うと、新品で買った場合に比べて耐用年数が短くなります。耐用年数が短くなるとそれだけ早く経費にすることができるようになります。そのため、中古資産は節税になると言われているのです。
300万円で新車を買った場合、6年かけて毎年50万円が経費になります。
300万円で3年落ちの中古車を買った場合、3年かけて毎年100万円が経費になります。
経費になる総額は新車でも中古車でも変わりませんが、中古車の方が早く経費にできます。
中古資産の耐用年数
中古で資産を買って事業のために使った場合は、その中古資産の耐用年数は、法定耐用年数ではなく、下記のように計算された耐用年数を使うことができます。
その中古資産を事業のために使い始めた時から、その後どれくらいの年数使用できるかという使用可能期間を自分で見積もった年数
使用可能期間の見積りが難しいときは、下記の方法で計算した年数法定耐用年数の全部を経過した中古資産は、法定耐用年数の20%の年数
法定耐用年数 × 20%
法定耐用年数の一部を経過した中古資産は、その法定耐用年数から経過した年数を差し引いた年数に、経過した年数の20%を加えた年数
(法定耐用年数 - 経過年数) + (経過年数 × 20%)
計算結果に出てきた1年未満の端数は切り捨てます。
計算結果が2年未満の場合は2年とします。
中古資産の耐用年数を計算するときの注意点
その中古資産を事業に使うために支出した資本的支出の金額がその中古資産の再取得価額(中古資産と同じ新品のものを取得する場合のその取得価額)の50%を超える場合には、中古資産の耐用年数ではなく法定耐用年数を使わなくてはいけません。
中古資産の耐用年数の計算は、その中古資産を事業のために使い始めた事業年度においてのみすることができます。その中古資産を事業のために使い始めた事業年度において中古資産の耐用年数の計算をしなかった場合は、その後の事業年度において中古資産の耐用年数の計算をすることはできないので、法定耐用年数を使うことになります。
4年落ちの中古車なら1年で経費にできます
4年落ちの中古車の耐用年数は
(6年 - 4年) + (4年 × 20%) = 2.8年
1年未満の端数は切り捨てるので2年になります
耐用年数2年の定率法の償却率は100%、つまり1年で全額経費にできます。このため税理士は、新車よりも中古車、中古車なら4年落ちをすすめるのです。
ちなみに、中古車のその他の年落ちの耐用年数はこのようになります。
| 年式 | 耐用年数 | 定率法の償却率 |
| 新車 | 6年 | 0.333 |
| 1年落ちの中古車 | 5年 | 0.400 |
| 2年落ちの中古車 | 4年 | 0.500 |
| 3年落ちの中古車 | 3年 | 0.667 |
| 4年落ちの中古車 | 2年 | 1.000 |
| 5年落ちの中古車 | 2年 | 1.000 |
| 6年落ちの中古車 | 2年 | 1.000 |
| 7年落ち以上 | 2年 | 1.000 |
| 東京都港区の税理士法人インテグリティ作成 | ||
1年で全額経費にできるといっても、月割で計算されるので、例えば決算月に中古車を買っても1か月しか経費にできず、残りの11ヶ月分は翌年の経費になってしまうことに注意してください。
また、中古車を買っても事業のために使い始めないと経費にできません。買っても納車がまだ、使わないで寝かせている場合などは経費にできないことにもご留意ください。
中古車による節税のポイント
新車でも中古車でもトータルで経費になる額は変わらないので、税金の額も変わりません。経費になる時期、すなわち税金を払う時期が異なるだけです。中古資産だと前倒しで経費にできるので、その分税金の支払いを後ろに繰り越す効果があるのです。
ファイナンス、資金繰りの基本は受け取るお金はなるべく早く、支払うお金はなるべく遅くです。税金の支払いを後ろに回して資金繰りを楽にしましょう。
社用車が必要である場合はもちろん構いませんが、節税のためにあまり欲しくもない車を買うのはやめた方がいいですね。税金を多少払ってでも手もとに現金を残した方が得策です。
おわりに
4年落ちの高級車を数年ごとに乗り換えている経営者さんも沢山いらっしゃいます。下落率が低い車であれば、資金繰りが急に厳しくなったときなどイザというときの保険にもなりますね。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。