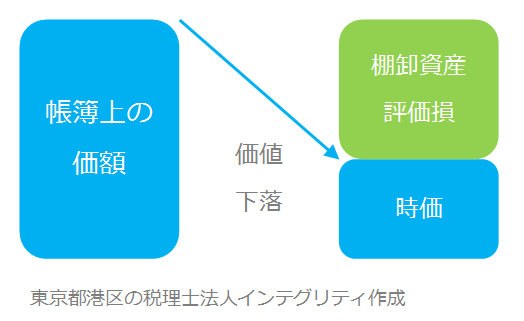はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
資本金の額はいくらになっていますか?通常は少ない資本金から会社をスタートして、会社の規模に応じて、自己資本比率などを考えながら増資をしていくことになると思います。しかし、単に体面が良い、金融機関のススメで、などの理由から、会社の規模に比べて資本金の額を高めに設定している場合も少なくありません。そのことで余分に税金を払っている可能性があります。
今回は、節税目線の資本金設定のステップ2として、資本金3,000万円以下の場合のメリットについて解説したいと思います。
資本金が3,000万円以下の場合の節税メリットは、中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除を受けることができることです。下記でもう少し詳しく説明します。
特定中小企業者
青色申告をしている会社で資本金が1億円以下の会社(大企業の子会社などは除きます)は中小企業者に該当して、そのうち資本金が3,000万円以下の会社のことを特定中小企業者といいます。
この特定中小企業者は、中小企業等投資促進税制における、中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除という税制優遇を利用することができるので、これにより節税することができます。
中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除
中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除とは、特定中小企業者が特定の新品の機械や設備などを買ったときに受けられる税制上の優遇措置で、購入額の7%に当たる金額だけ、納めるべき法人税の額から差し引くことができる制度をいいます。(法人税の金額の20%が上限です。)
300万円の機械を購入した場合は、
300万円×7%=21万円だけ法人税を節税することができます。
このように税額控除というものは、所得控除と異なり、直接的に税金を減らしてくれるので節税効果が高い節税方法といえます。
おわりに
中小企業者等が機械等を取得した場合の税額控除を受けるためには、適用される時期、対象となる業種や資産など細かい要件に合致するとともに、提出しなければならない書類もあります。また、この中小企業等投資促進税制は拡大も予定されているので、実際に利用する場合は税理士に相談することをオススメします。
資本金に関しては、下記も合わせて参照ください。
節税目線の資本金の決め方-1-1,000万円未満
節税目線の資本金の決め方-3-1億円以下
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。