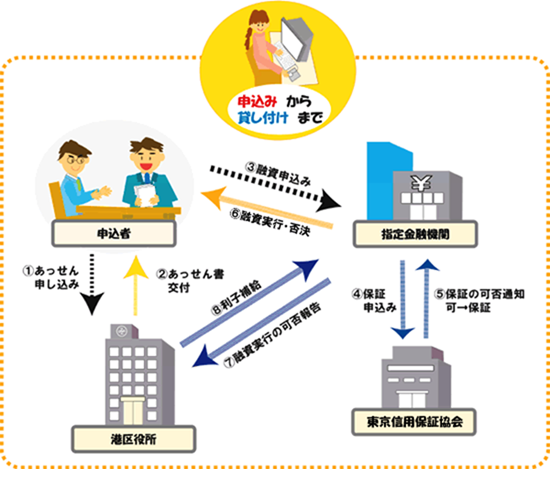はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
今回は、フリーランス、個人事業主の方が納める税金の種類についてです。
法人(会社)については「会社(法人)が納める税金の種類」を参照ください。
税金の種類
会社勤めの時代は給与天引きで会社が納付してくれていた税金ですが、フリーランス、個人事業主としてスタートしたら、今度は自分で税金を納付しなければいけません。事業を行うにあたって生じる一般的な税金にはこのようなものがあります。一般的なものでもたくさん種類があって迷っちゃいますね。正確性よりも、理解しやすいように簡単に説明したいと思います。
| 国税(国が課税する税金) |
| 所得税 |
「所得(利益)」にかかる税金で税務署に納めます。 |
| 特別復興所得税 |
「所得税に追加」される税金で税務署に納めます。 |
| 消費税 |
「消費」にかかる税金で税務署に納めます。 |
| 地方税(地方自治体が課税する税金) |
| 個人事業税 |
「所得(利益)」にかかる税金で都道府県税事務所に納めます。詳細は「個人事業税とは | フリーランス・個人事業主の税金」を参照ください |
| 住民税(都道府県民税) |
「所得(利益)」にかかる税金で市町村民税と併せて市町村に納めます。 |
| 住民税(市町村民税) |
「所得(利益)」にかかる税金で市町村に納めます。 |
| 地方消費税 |
「消費」にかかる税金で消費税と併せて税務署に納めます。 |
| 固定資産税 |
「土地や家屋の保有」にかかる税金で市町村に納めます。 |
| 償却資産税 |
「土地家屋以外の資産の保有」にかかる税金で市町村に納めます。 |
| 出展:税理士法人インテグリティ調べ |
所得税
国税庁のホームページには、「所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、1年間の全ての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用し税額を計算します。」と書かれています。分かるようで、よく分かりませんね。
簡単に言うと、所得税とは「1年間の”もうけ”から、皆さん個人の事情を考慮して、そこに税率をかけて計算」する税金です。自分で税額を計算(確定申告)して、税務署に納める国税です。
売上ではなく所得(利益、もうけ)にかかる税金なので、売上100円-費用90円=利益10円だとすると、100円ではなく10円にかかる税金です。
個人の事情を考慮とは、家族の人数、医療費の額などです。同じ利益を稼いでいたとしても、養う家族が多い人の方が、所得税は安くなります。
なお、平成25年から平成49年まで、東日本大震災復興のための財源確保のため、所得税の2.1%を復興特別所得税として納付します。
消費税、地方消費税
消費税は、モノやサービスの「消費」にかかる税金で、国税である消費税と地方税である地方消費税の2種類ありますが、納付はまとめて税務署で行います。
消費税を支払う人は消費者(カフェのお客さん)ですが、納付する人は事業主(カフェ)です。カフェお客さんはコーヒーを飲んでコーヒー代金と消費税をカフェに支払います。また、カフェでもコーヒー豆の仕入れなどを行ったときには豆代金とともに消費税をコーヒー豆屋さんに支払っています。このようにカフェではお客から「預かった消費税」とコーヒー豆屋さんなどに「支払った消費税」があります。そして、カフェは「預かった消費税」から、「支払った消費税」をマイナスした額を計算して税務署に納めます。
よく勘違いするところですが、お客から受け取った消費税は、カフェの儲けではなく、あくまで預かっているもので後日税務署に納付するものなのです。
売上が小さい場合は、免税事業者として消費税を納める必要がございません。詳しくは税理士に聞いてみて下さい。
このように税金を支払う人と税金を収める人が異なる税金を間接税といいます。
個人事業税
個人事業税は、個人が都道府県内で事業を行っていることに対して税金がかかるものです。言葉は悪いですが、都道府県内で商売をやっているんだから、もうけに応じて都道府県にショバ代を払えってことですね。
なお、もうけが少ない場合(290万円以下)は、個人事業税は課税されません。
確定申告をすれば、自分で税額を計算する必要はありません。確定申告にもとづいて都道府県が税額を計算して、これだけ払って下さいと通知を送ってきます。
住民税
住民税は、所得税と同じく、もうけにかかる税金です。
確定申告をすれば、自分で税額を計算する必要はありません。確定申告にもとづいて地方自治体が税額を計算して、これだけ払って下さいと通知を送ってきます。都道府県分と市町村分を併せて市町村に納付します。
この住民税、けっこう負担が大きいです。特にもうけが少ないうちは所得税よりも住民税が高くなっています。なぜかというと、所得税は儲けが増えると税率が上がる、いわゆる累進課税となっていますが、住民税は儲けの額は関係なく一律で税率が決まっているからです。
また、住民税は前年の儲けに対して税金がかかってきます。そのため、会社勤めを辞めて独立、独立当初は売上も少ないのに、前年の給料をもとにして住民税が発生するため、納付に苦労した、という話もよく聞きます。
固定資産税
固定資産税は、1月1日に土地、家屋を持っている人が、その土地、家屋の価格をもとに算定される税額を、その土地、家屋がある市町村に納める税金です。持っている人なので、貸している人は該当しますが、借りている人は関係ありません。
市町村が登記簿をもとに持っている人を特定して、税金を計算して通知してくるので、その通知を待ちましょう。
償却資産税
償却資産税は、1月1日に土地、家屋以外の資産を持っている人が、その資産の価格をもとに算定される税額を、その資産がある市町村に納める税金です。何でも資産に当てはまる訳ではなく、カネ、土地、家屋、車以外の値段が高い機械や装置などをイメージして下さい。
登記がある土地、家屋と異なり、その資産を持っている人を市町村は特定できません。そのため資産を持っている人は市町村に教えなければいけません。市町村はそれをもとに税額を計算して通知してきます。
おわりに
港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として起業、開業をお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。